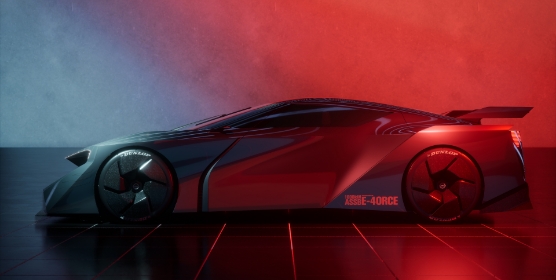レジェンド 08:EVがエネルギーのネットワーク化を加速する、堀江 英明。

堀江 英明
1957年広島県広島市に生まれる。1976年に広島大学教育学部付属高等学校を卒業後、東京大学教養学部理科Ⅰ類へ入学。1980年に東京大学工学部船舶工業科へ進学し1983年に卒業。同年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻理学修士課程に入学し1985年に修了。日産自動車へ入社する。
中央研究所の材料研究所へ配属後、1990年に車両研究所へ異動し、高性能電源システムの研究開発に携わる。1999年に総合研究所の主任研究員、2005年に総合研究所第一技術研究所の主管研究員、2006年には電動駆動研究所の主管研究員、以後、2007年から2010年まで東京大学人工物工学研究センター准教授、2011年に東京大学生産技術研究所特任教授、2012年にシニア・イノベーション・リサーチャー(SIR)に就任し現在に至る。
「自動車の免許は入社してから取りました。自動車メーカーに入ったし免許くらいは持ってないとまずいかなと(笑)。でも、クルマ自体には興味があって、小さいころはクルマの絵ばかり描いていました。初めて買ったクルマはブルーバード。結婚して子供ができたので。必要に迫られたというよりは、ロジスティック上迫られたという感じです(笑)」
サラリーマン博士の誕生


「会社では自動車用バッテリー、大学では定置用の研究と、コンプライアンスをちゃんと守っています」 インタビューの冒頭、堀江からそう説明を受け、彼が先進技術の研究開発というデリケートな立場にあることを認識した。
1957年4月に広島県広島市生まれた堀江は高校までを広島で過ごし、東京大学教養学部理科Ⅰ類に入学する。東大に入学し東大の特任教授になるような人物は、図抜けた才覚のある子供だったに違いない。例えば夏休みの自由研究で、先生ですら理解するのが容易ではない実験をしてしまったとか。


大学時代、文系の人よりもたくさんそれ系の本を読んだんじゃないかと自負する堀江は、大学時代の後半では物理をやっていこうと考える。それにはもちろん、彼なりの理路整然とした理由があった。 「物理が、世の中の基本だと思いました。昔ならそれは宗教だったのかもしれませんね」
結局大学院まで進み、1985年に東京大学大学院理学系研究科物理学専攻理学修士課程を修了する。そのまま、研究者としての道を選ぶこともできたが、社会に出ることに。
「大学もそれはそれで大変立派な社会なのですが、日本ではしばしばそう見られない部分があるかもしれませんね。企業に勤め収入を得て生活する場が社会。日産自動車を選んだ理由ですか? 日産は自動車だけでなく宇宙航空や海洋もやっていたし、交通システムにも興味がありました。社会貢献の一役を担えるかと思ったのです。それと、これは個人的にとても重要なのですが、追浜が海のすぐ近くにあったので(笑)。海が大好きなのです。学生時代に海と入道雲を一週間、見続けたこともありました(笑)。そこに理由は特になく、ただ、海が好きだったのです」

6年かけてドクター論文を書き上げる

入社後は材料研究所に所属、触媒開発に携わった。1985年と言えば、触媒の研究開発は頂点の時期。ポルシェやBMWが採用を狙い研究開発をしていたメタル単体触媒を、日産は世界に先駆け、しかも量産車のスカイラインやローレルなどに投入した。その研究開発にも堀江は関与することができた。
「実は化学があまり好きではなかったので、当初はちょっと困りました。でも大変に勉強になりました。化学工学について徹底的に学ばせていただいて、それが後の電池開発に大変役に立ちました」
材料研究所で数年が経ち、このまま触媒を極めるのか、あるいは新たなものを追い求めるのか、そんなことを考えていた頃、堀江は聞き慣れない言葉を耳にする。それが「ZEV」、ゼロエミッションビークルだった。「ゼロエミッションって電気自動車?」くらいの知識しかなかったものの、なんとなく興味を持ったという。同じ頃、日産は車両研究所で電気自動車のチームを立ち上げる。堀江はそこへ誘われた。
「1990年2月1日に配属されました。当時、電気自動車用電池の担当は自分ひとりでした。上司からは、あらゆる電池の可能性を探って欲しい、10年やって欲しいと。10年は長いなと思っていましたが(笑)、いつの間にか20年以上経ってしまいました。物理専攻ならインバータかモーターを担当するのが普通ですね。でも、電気自動車を司るのは電池に違いないし、電池はまだ開発途上だったので、最初に土俵を作ることができれば、後発組はその土俵で戦わざるを得ない。先行する意味があると考えました。こんな偉そうなことを言っていますが、電池のことはほとんど何も知らなかったので、いちから勉強を始めました」

座間事業所でのバッテリー生産ライン。

車両研究所で「高性能電源システムの研究開発」に取り組む一方で、たまに大学の恩師のところへ顔を出していたところ、「ムダにはならないのだから、ドクターを取ってみたらどうか」と打診を受ける。
「それがきっかけで、週末はほぼ徹夜。6年かけて論文を書き上げました。審査の先生の一人からは冗談で、内容は博士論文3本分ありますねと言われました。もちろん、会社のリソースはまったく使わず、会社にも報告していませんでした。会社に言ったのは、1999年に博士号を取ってからです(笑)」
こうして、自動車会社では稀な“サラリーマン博士”が誕生したのだった。


EVだからできること



内燃機とEVの決定的な違い
私たちにとっての“電池”とは、電気を溜める“箱”くらいの認識しかない。しかし、堀江の話を聞いていると、彼は電池をまったく別の何かとして捉えているように思えた。堀江にとって電池とは、どういう存在なのだろう。
「そうですね、リチウムイオン電池を他の電池と同じようにくくられてしまうことには若干抵抗があります(笑)。いま、世界はネットワークの時代です。情報革命に続いて、電気エネルギーも、このネットワークで使う時代が来るのではないでしょうか。



「自動車は年間で7000万台くらい生産され更に今後も増えてゆきます。これを最大出力で考えてみると、1台当たり100kWを発生するとして7000万台がすべてEVだと仮定すれば、その出力は原発7000基分にも相当します。自動車産業とはこのようにとてつもないポテンシャルを秘めた産業なのですが、それが個々に走り回っていると実感も湧かないでしょうし、EVの有効な使い方とは言えません。ネットワークで繋げて共有して初めて、EVというクルマの真価が発揮されるのです」
そう語る堀江の目には、そんな未来のネットワーク社会がすでに具体的に映っているように見えた。
渡辺
慎太郎
/
Shintaro
Watanabe
1966年東京生まれ。アメリカの大学を卒業後、自動車専門誌「ル・ボラン」の編集者を経て1998年にカーグラフィック編集部へ。2003年に退職し、編集プロダクション「(有)MPI」の代表を務めるとともに、自動車ジャーナリストとしても活動を始める。現在はカーグラフィックの編集長も務める。